 🏠
🏠
 🏠
🏠

スマホのボディーにはアルミニウムに着色した着色アルマイトが使われています。
アルミニウムをアノード酸化して、表面に多孔質酸化皮膜をつくり、その孔に 染料を入れて吸着します。
1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 ) 奥野製薬 保土ヶ谷化学米沢高等工業学校 が山形大学工学部になってから工学部には高分子、化学、機械、電気の学科があり、高分子化学(H)、材料(T)、応用化学(C)、化学工学(K)、機械工学(M)、精密機械(S)、電気工学(E)、電子工学(A)の専修コースに分かれていた。 そのうち化学系には応用化学系( C1 :電気化学 、C2:分析化学、C3:天然物、C4: 石油化学)があり化学工学系(K1:流体・伝熱、K2:反応工学、K3:粉体工学、K4: プロセス制御)というように それぞれの学問体系に研究室が割り振られていた。 その後、C5:合成化学、C6:無機材料化学、C7:有機材料化学の研究室が増えた。
この講義は、松木健三先生が電気化学として担当されていました。その後、 仁科辰夫先生がご担当されていましたが、一時期物理化学に併合されました。電気化学は工学部の応用化学であり、物理化学は理学部の理論化学なので、本来趣を異にするものです。そのあと吉田司先生が着任されて電気化学として復活した際、あらためて仁科辰夫先生と立花が半分をオムニバス形式により担当していました。その後、吉田司先生が他学科に移られたため、再び仁科辰夫先生と立花で、複数教員担当方式により全コマ担当するに至りました。さらに時代の要請をうけ「電気化学」から「エネルギー化学」へと科目名の変更がなされました。仁科辰夫先生のご退職に伴い、後継者不足から、立花が単独で担当することになりました。工学にはなくてはならないエネルギーとモノづくりの関係をについて、よりよい講義ができればと思います。よろしくお願いいたします。
| 西暦 | 出来事 |
|---|---|
| ものさし (長さ) | |
| 1604 | ◇ ガリレイ(伊)落体の法則を発見、地動説を発表。 |
| 振り子時計 ( ⏱ 時間) | |
| 1687 | ◇ ニュートン (英)、万有引力の法則を発見。 |
| 温度計 ( 温度) | |
| 1760 | ワット(英)、 蒸気機関🚂を発明 |
| 1788 | クーロン (仏)静電気に関するクーロンの法則を発見。 |
| ボイルシャルルの法則 🔥⇒💪 | |
| 1800 | ボルタ(独)ボルタ電堆 |
| 1820 | アンペール(仏)、電流の発見 |
| 1831 | ヘンリー(米)モーターの発明。 |
| 1833 | ファラデー(英)電気分解の法則を発見 |
| 1840 | ジュール (英)電流の熱作用の法則を発見。 |
| 発電機 💪⇒⚡ | |
| ◇ 20世紀 | |
| 1905 | アインシュタイン(独)特殊相対性理論 |
| 1924 | ボーズ・アインシュタイン統計 |
| 1926 | シュレーディンガー(独)波動力学の確立 |
| 1931 | ウィルソン(英)半導体の理論 |
| 1948 | トランジスタ |
| 1960 | レーザーの製作、マイマン(米) |
| 1966 | 光ファイバーによる 通信、カオ(中)、ホッカム(英) |
| 1970 | CCDセンサーの発明、ボイル(加)、スミス(米) |
| ◇ 1980 | |
| kWh、 J | 関係式 | 示強性変数 | 示量性変数 | 物質量あたり マクロ |
粒子あたり ミクロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🧪 化学エネルギーG | ⊿G=⊿H-T⊿S | 化学ポテンシャル | 物質量〔mol〕 | アボガドロ数
NA |
|
| 🔥 熱エネルギー |
🖱
Q=
TS
RT
|
温度 T 〔K〕 | エントロピー S 〔J/K〕 | 気体定数 R 〔J/K・mol〕 | ボルツマン定数 kB 〔J/K |
| 💪 力学的エネルギー E | 🖱 W= pV | 圧力 p 〔Pa〕 | 体積 V 〔m3〕 | 理想気体のモル体積 x 〔L/mol〕 | |
| ⚡ 電気エネルギー E |
🖱
E=VQ
E=nFE
|
電圧 V 〔V〕 | 電気量 Q 〔C〕 | ファラデー定数 F 〔C/mol〕 | 電気素量 e 〔C〕 |
| 🌟 光エネルギー E | E=hν | 振動数 ν 〔Hz〕 | プランク定数 h 〔J・s〕 |
エネルギーは、相互に エネルギー変換できます。 エネルギーは保存則でなくなりませんが、有効な仕事として利用できるエネルギー(エクセルギー)の割合は減っていき、廃熱(アネルギー)の割合が増えていきます。 その意味で、熱エネルギーはエネルギーの廃棄物と言えます。
状態量
2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライ フスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、 グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、 全ての学習者が、持続可能な開発を 促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。
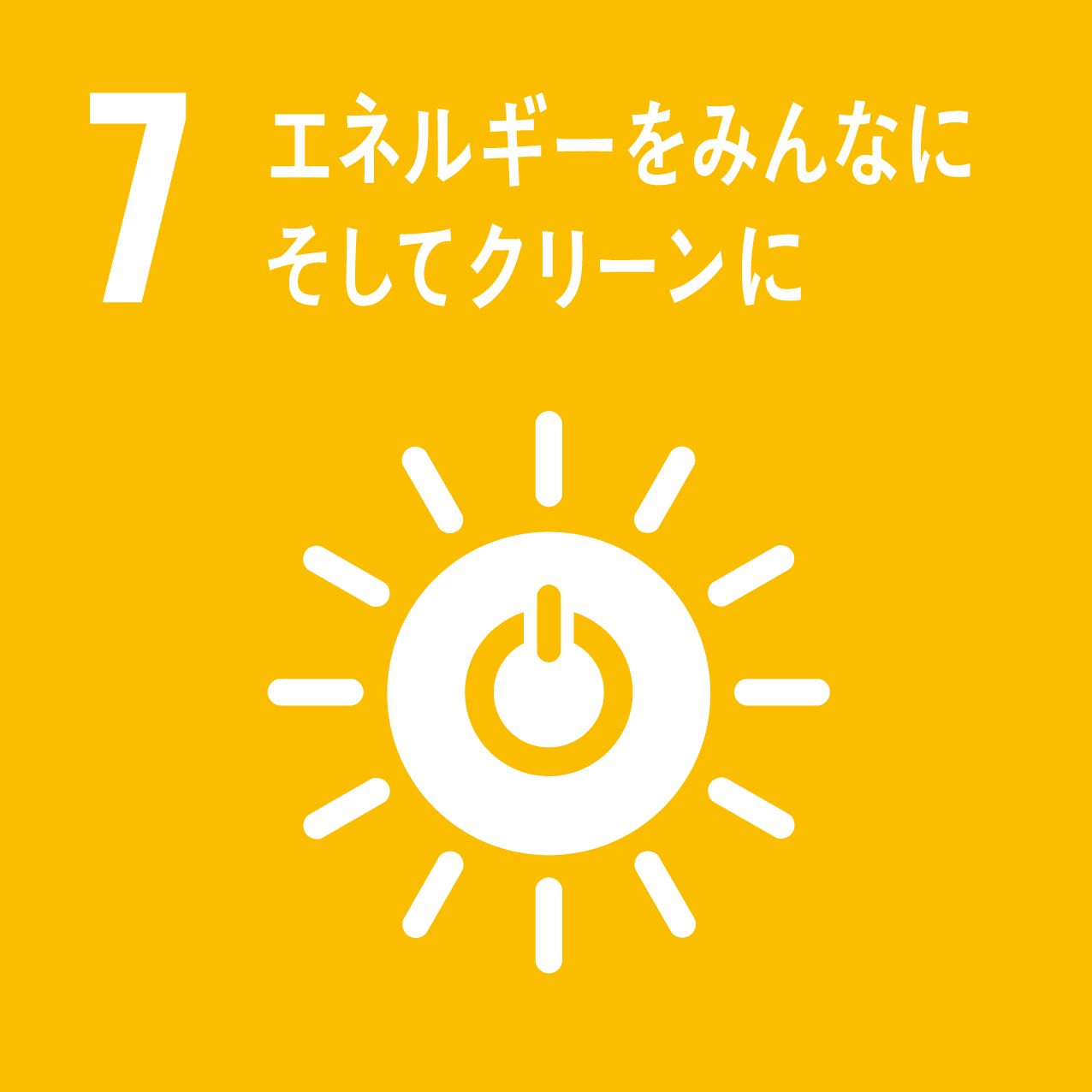
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。
世界人口のおよそ4分の1が電気のない生活をしており、それ以上の人々が料理や暖房のための現代燃料を利用できない。
🔷
SDG 9は金融、テクノロジー、技術の支援、研究、 情報通信技術へのアクセス増大によって達成される。
2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。

SDG 12は、環境に有害な材料の管理に関する特定の政策や国際協定のような措置を通して、消費や生産パターンを促進することを目指す。ゴールが2020年までに達成したいと目指すターゲットは、そのライフサイクルを通して化学物質や 廃棄物を環境上健全に管理し、 それらが大気、水、土壌に放出されるのを大幅に減らし、人間の健康と環境に対する悪影響を最低限に抑えることである。
「電気化学?なんか電気ってつくと難しそう・・・」
「なんだか学問を難しいとか苦手とかで議論するのはさびしいなあ・・・じゃあ、たとえばさ、金属のナトリウムを単離するのにどうすればいいと思う?」
「・・・」
「理屈ではまあ食塩、塩化ナトリウムの中のナトリウムイオンを還元すればいいんだけど・・・」
「・・・」
「ヒドラジンとか強力な還元剤と反応させたら単離できると思う?」
「うーん、どうだろう?」
「薬品を使った還元では限度があるんだよね・・・そこで電気の登場。電圧をかければかけるだけ好きなだけ強力な還元力が得られるんだ」
「へー」
「電気化学の前半の講義ここでは主に
物質化学工学実験Ⅱ
で出てくるテーマの予習になるような内容を取り扱います!
電気回路に出てくる受動素子の種類は電気抵抗(レジスタンス)、静電容量(キャパシタンス)、インダクタンスの三種類しかありません。
化合物を表すのに化学式を使います。化学式には組成式やイオン式などがあります。 ダニエル電池 電池式 Zn | Zn2+ || Cu2+ | Cu 化合物を化学式で表すように、電池を表すには電池式があります。電池式はアノードを左側に書くのが慣例です。 電池式の縦棒(|)は相と相との界面を表しています。 界面の厚みはないものとみなします。 ? Zn | Zn2+ || Cu2+ | Cu ??? ( * ) 電池には電極があります。酸化が起きる極をアノード、還元が起きる極をカソードと呼びます。 以前はアノードを陽極、カソードを陰極と呼びましたが、正極と陽極がまぎらわしいのでアノードと呼びます。 アノードは電流が外部回路から流れ込む極です。カソードは電流が外部回路へ流れ出す極です。 アノード、カソードは電流の向きに注目した呼び方です。 それとは別に正極と負極という呼び方があります。 電位の高い極を正極、電位の低い方を負極と呼びます。 正極、負極は電位の高低に注目した呼び方です。

このマークは本説明資料に掲載している引用箇所以外の著作物について付けられたものです。
銅めっき 米沢高等工業学校本館から 銀電量計を探してみよう。
アノードもカソードも銅だったら、理論分解電圧は何Vになるか?