 🏠
🏠
 🏠
🏠
日本の食べ物は海とかかわっている。 コンブ、ワカメ、ヒジキ、ノリ、テングサ・・・英訳が大変だ。 おっと忘れちゃいけないカツオブシ。 たぶん英訳が大変なものほど和食なのだろう。
| 含有成分 元素 | 単肥の例 | 原料 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| 🏞 窒素 | 硫安(硫酸アンモニウム)・尿素・硝安(硝酸アンモニウム)・塩安(塩化アンモニウム)・石灰窒素 | 🏞 アンモニア 1 ) 2 ) 3 ) | 葉肥 * | |
| リン | リン酸カルシウム・過リン酸石灰・ | リン酸 | 果肥 | |
| カリウム | 硫酸カリウム、塩化カリウム | 鉱物 | 根肥 |
肥料には、肥料の三要素を一成分含む単肥と、二要素以上含む複合肥料に分けられます。また複合肥料は、配合肥料と化成肥料に分けられます。化成肥料は、肥料の三要素のうち、二要素以上を化学合成で作ったものです 4 ) 。
化学肥料の成分を調べなさい。また有機農業推進法について調べなさい。食料問題について調べなさい。これら3つの調査結果から、これからの食に化学がどうかかわるべきかを述べなさい。
DDTは学生の卒業研究で発見されました。殺虫剤として発明したのは、P.H.ミュラー博士(スイス)で、1948年にノーベル医学・生理学賞を受賞しています。 DDTの代謝生成物であるDDE、DDAなどは、体内に蓄積され、生物濃縮を起こします。 わが国では、 1968年(昭和43年)に 農薬(製造販売)会社が自主的に生産を中止し、1971年(昭和46年)には販売が禁止されました。 世界的にも、環境への懸念から先進国を中心に、2000年までには、40カ国以上でDDTの使用が禁止・制限されています。 しかし、その一方で、マラリアが猛威を振るう亜熱帯や熱帯地域の多くの国々では依然としてDDTを必要としています。
コンビニのゆで卵の直径の公差。 適量、少々、お好みで。ビール2~3本。
| 分類 | 種類 | 構成 | 原料 | 応用例 |
|---|---|---|---|---|
| 単糖類 | ブドウ糖 | 果物、血液 | ||
| 果糖 | 果物、蜂蜜 | |||
| 二糖類 | ショ糖 | ブドウ糖+果糖 | さとうきび | |
| 乳糖 | ブドウ糖+ガラクトース | 牛乳 | ||
| 麦芽糖 | ブドウ糖+ブドウ糖 | 水あめ、いも、 麦汁 | ||
| 多糖類 | デンプン | ブドウ糖 | 穀類、いも | |
| グリコーゲン | ブドウ糖 | 筋肉、肝臓 | ||
| セルロース | ブドウ糖 | 植物 本体 |
セルロースなどは、 高分子化合物です。
| 分類 | 分類 | 名称 | ケン化価 | ヨウ素価 | 成分 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動物性油脂 | 陸産動物油脂 | 豚脂 | ||||
| 水産動物油脂 | イワシ油 | |||||
| 植物性油脂 | 乾性油 | アマニ油 エゴマ油 | 塗料 | |||
| 半乾性油 | 綿実油 菜種油 | |||||
| 不乾性油 | オリーブ油 | |||||
| 植物脂 | パーム油 木ロウ | |||||
| ロウ | 液体ロウ | マッコウ鯨油 | ||||
| 固体ロウ | ミツロウ |
産業革命以前は、 燃料として、油脂が使われてきました。
👨🏫 中分類09食品業界(中分類09 食料品製造業)|
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
|
高級アルコール
|
高級脂肪酸
|
硬化油
|
グリセリン
|
石鹸
|
ボイル油
|
|
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
↓
|
|
合成洗剤
|
界面活性剤
石鹸
|
マーガリン・化粧品
|
洗剤
|
油性
塗料
|

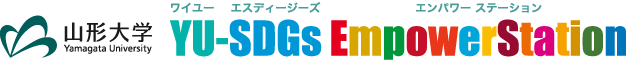
| 加工方法 | 原料 | 加工食品 | |
|---|---|---|---|
| 物理的 | 真空凍結乾燥 (フリーズドライ) | インスタントコーヒー | |
| 加熱乾燥 | 小麦粉 | インスタントラーメン | |
| 脂肪分離 | 牛乳 | バター | |
| 化学的 | 塩析 | 大豆 | とうふ |
| 水素添加 | 動植物油 | マーガリン | |
| 乳化 | 食酢、卵、油 | 👨🏫 マヨネーズ | |
| 生物的 | 発酵 | 牛乳 | チーズ |
| 発酵 | 大豆 | みそ、しょうゆ、 納豆 | |
| 発酵 | デンプン | 酒類 ビール | |
食品の原料は天然資源です。
6 ) 👨🏫 ISO22000(HACCP・ハサップ・ハセップ)| 目的 | 背景 | 特徴 | 例 | |
|---|---|---|---|---|
| 物質の移動 | 輸送 | 溶かす | ||
| 加圧 | 💪 第一次産業革命 | つぶす、圧力釜 | ポンプ で気体を圧縮する。 🏞 アンモニア | |
| 熱の移動 | 加熱 | 🔥 | 温度 |
炉
ボイラー
茹でる、煮る、蒸す 🏞 製鉄 1500℃ |
| 冷却 | 💪 第一次産業革命 | 冷ます 酸素 | ||
| 固体の処理 | 撹拌・混合 | 混ぜる | ||
|
固体と液体 液体と液体 |
溶解 | 溶かす | ||
| 撹拌・混合 | 混ぜる | |||
| 粉砕 7 ) ・ 解砕・分散 8 ) | 砕く、 👨🏫 マヨネーズ 、チョコレート | |||
| 濾過・ 沈降・ 乾燥 | 干す | |||
| 再結晶・塩析 | ||||
| 気体・ 液体・固体 中からある成分を取り出す | 分離・抽出 | 濾す | ||
| 蒸留 ・分留 | 🏞 ナフサ ガソリン ウイスキー シリコン | |||
| 電気を使う | 電解製造 電解・電析 | ⚡ 第2次産業革命 | 🏞 アルミニウム q.64 めっき | |
| 電解精錬 | ||||
| 電気透析 | かん水 | |||
| 光を使う | 露光 | ⚡ 第3次産業革命 | フォトリソグラフィー |
化学反応を起こさせる操作すなわち反応操作(unit process)のほかに、いろいろな物理的な操作を必要とする。この物理的な操作を単位操作(unit operation)という 9 ) 10 ) 11 ) 。
| 項目 | 数値 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 熱量: | 351 | kcal | 必要エネルギー量を 計算BMI22を目指そう。 |
| たんぱく質 | 10.5 | g | ケルダール法など * |
| 脂質 | 13.6 | g | |
| 炭水化物 | 14.6 | g | |
| 食塩相当量 | 4.9 | g | 一日1日の摂取基準量5g以下を目指そう |
| ビタミンB1 | 0.19 | mg | |
| ビタミンB2 | 0.32 | mg | |
| カルシウム | 105 | mg |
食品表示法 では、内容量又は固形量及び内容総量の表示が義務付けられていいます。 内容重量はグラム又はキログラム単位で、内容体積はミリリットル又はリットル単位で、内容数量は個数等の単位で、単位を明記しなければなりません。 計量については、計量法に従ってください。 また、加工食品の栄養成分の量および熱量の表示が義務付けられています。 一定の値又は下限値及び上限値を示されなればいけません。 表示された一定の値を基準として、許容差の範囲に入っていなければいけませんが、 栄養成分表示の近接した場所に、「推定値」又は「この表示値は、目安です。」のいずれかの文言を含む表示をした場合、 合理的な 推定により得られた値を表示値として使うことができます。
熱量は、成分の熱量から推定します。 *
こねる、平たくする、ロールで厚み1mmに延ばす、切り出す、蒸す、枠づめ、油揚げ、、、 12 )
食品表示法により 消費者への品質表示 が義務付けられています。
栄養成分表示 * 👨🏫 インスタントラーメン発明記念館キンビラゴボウ。うまいね。 佃煮。美味しい水がないと煮物は発達しない。 モンスーン気候がもたらす急峻な川と水。 羊羹はあんこと寒天から作る。寒天は海の恵みと冬の厳しさからできる。
雪解け水。梅雨。湿気。 日本の気候はカビとの戦い。
食べ物に使う無機化合物| 分類 | 成分 | 特徴 |
|---|---|---|
| 醸造 | 酒、 ビール、 ワイン 14 ) | |
| 発酵食品 | みそ、醤油、酢、古漬け、チーズ、ヨーグルト | |
| アミノ酸 | グルタミン酸 | |
| 核酸 | イノシン酸 | |
| 有機酸 15 ) | クエン酸、乳酸 | |
| 生理活性物質 | ビタミン、ホルモン | |
| 抗生物質 | ペニシリン |
発酵工業は、温度や圧力が常温常圧に近く、使用エネルギーが少なく、 設備も簡単です。 反面、生成物に微生物や副生物が混入するので、分離や精製に手間がかかり、反応時間が長くなります 16 ) 。
日本酒とコウジカビ。 豆腐。にがりは海水から塩をとった残渣から。 寿司。日本酒と酢にする発酵。 納豆。煮るという操作で枯草菌だけ残す技術。 味噌は豆と米とコウジカビと酵母と乳酸菌。 カルピス、ヤクルトは乳酸菌。日本初。
納豆発祥の地。わずかに残った兵糧の大豆が雪で湿り気を帯び、馬の体温で暖められたのが納豆のはじまりであるといわれています。
👨🏫 京田辺/酬恩庵一休寺@京都府京田辺市 👨🏫 金澤柵(金澤八幡宮)@秋田県横手市 👨🏫 生活と化学―油脂、炭水化物、タンパク質― 👨🏫 平安末期 納豆伝説 発酵 👨🏫 食品&飲料発酵槽は、 ステンレスなどで作られています 18 ) 。 19 )
発酵 👨🏫 キリンビール株式会社-金沢工場 👨🏫 キリンビール株式会社-横浜工場@神奈川県 👨🏫 【DF】【見学】サッポロビール静岡工場 👨🏫 アサヒビール福島工場 👨🏫 サッポロビール博物館
ブドウには、ごく微量ですが酒石酸(しゅせきさん)が含まれています。ブドウからワインを醸造すると、ワイン中に沈殿する滓にも、貯蔵する酒ダルの周壁にも、白い小さな結晶体が生じます。この滓や周壁の酒石酸が粗酒石(そしゅせき)です。また、ワインの液中にも酒石酸が混在し、ワインの搾り粕にも酒石酸が混在しています。ワインの液中や絞り粕から酒石酸を採取するには普通、脱酸用石灰を添加し、酒石酸石灰として採取する方法がありました。しかし、手っ取り早いのはやはり、周壁や沈殿滓の粗酒石を直接採取する方法でした。採取した粗酒石に加里ソーダを化合させると、酒石酸加里ソーダという少し大きな結晶体が精製されます。これがロッシェル塩と呼ばれるもので、山梨県に所在の「サドヤ醸造場」が国内で唯一、製造が可能でした。
ロッシェル塩は、音波をすばやく捉える特性があり、第2次世界大戦ではドイツがいち早くこれを採用して音波防御レーダーを開発、艦船に装備して、潜水艦や魚雷に対処する兵器とし、効果を発揮していました。
日本の海軍は昭和17年(1942)6月、中部太平洋のミッドウエーの海戦で、航空母艦4隻を失う大打撃を受けます。敗退直後から、海軍では同盟国のドイツに兵員を派遣し、ロッシェル塩を利用した探査技術を習得させ、艦艇の戦備を強化することにしました。昭和18年初頭から、海軍は全国のワイン醸造場に粗酒石の採取を働きかけ、粗酒石は山梨県の「サドヤ醸造場」に集めロッシェル塩を精製し、精製品は東芝などの大電機メーカに依頼して、対潜水艦用の水中聴音機の量産態勢を構築しました。水中聴音機は、まさにブドウから作る兵器です。
国税庁HPより *
醸造技術としては比較的簡単な方である。 つきつめると技術というより芸術というものであると言える 20 ) 。
樽| 材料 | 用途 | 特徴 スケール |
|---|---|---|
| セラミックス | 土器 | |
| 甕(陶磁器) | ろくろによる成型、焼成 | |
| 木材 | 樽、桶 | 鋸、鉋による切削加工 |
| 鉄鋼 | 茶釜 レトルト釜 ステンレス槽 スチール缶 | |
| アルミニウム | アルミ缶 | |
| ガラス | びん 、 ガラス器具 | |
| プラスチック | PETボトル | |
| 複合材料 | FRPタンク 反応槽 |
気体や液体を保持するには 固体材料で成型された容器が必須です。

木桶が、普及するには、鉋(かんな)や鋸(のこぎり)の鉄鋼を使った刃物の技術が必要であった。また刃物には、砥石を使った研削加工の技術が必要でした。
👨🏫 酒造資料館 東光の酒蔵@山形県米沢市和食は世界遺産になりました。 和食は、土器と水とともに発展しました。 日本の土器は、世界史でも、かなり早い時期です。 どんぐりを灰汁抜きして水で煮て食べるには、土器がないとです。 ヨーロッパで陶磁器が使われるのは、18世紀ごろです。
21 ) 👨🏫 食とくらしの小さな博物館@東京都港区 👨🏫 下町風俗資料館@東京都台東区上野公園
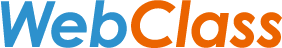

麻酔は、人為的な薬物中毒です。 通仙散の麻酔は、スコポラミンの急性中毒 22 ) 。 しかし、華岡青洲は、通仙散の全身麻酔によって、数々の外科手術を施術しました。
通仙散の完成には、進んで自らを人体実験に捧げた妻と母がありました。 華岡青洲の愛を奪い争う二人の助成の心の葛藤も見逃せません 23 ) 。
チョウセンアサガオはゴボウと間違えやすい有毒植物です 24 ) 。
薬人を殺さず薬師人を殺す(くすりひとをころさずくすしひとをころす) という諺があります。 毒と薬は紙一重であり、人を殺すのは、医者であり、薬剤師であり、エンジニアなのです。 危険なものを安全につかいこなすことが技術というなら 25 ) 、エンジニアには毒を薬として使う知識が必須です。 無知ほど危険なことはありません。
植物
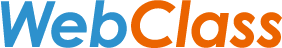



野村正勝・鈴鹿輝男
最新工業化学―持続的社会に向けて―
講談社サイエンティフィク
目次
松林光男、渡辺弘,
イラスト図解 工場のしくみ
,日本実業出版社
山下正通、小沢昭弥, 現代の電気化学,
丸善
,
目次
(2012).