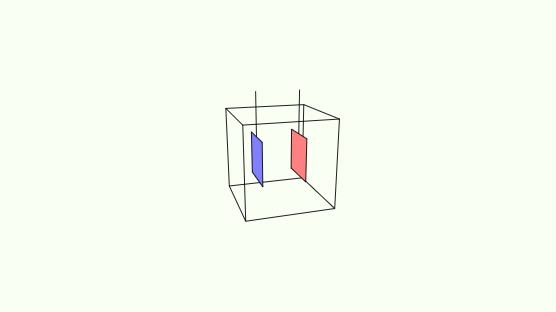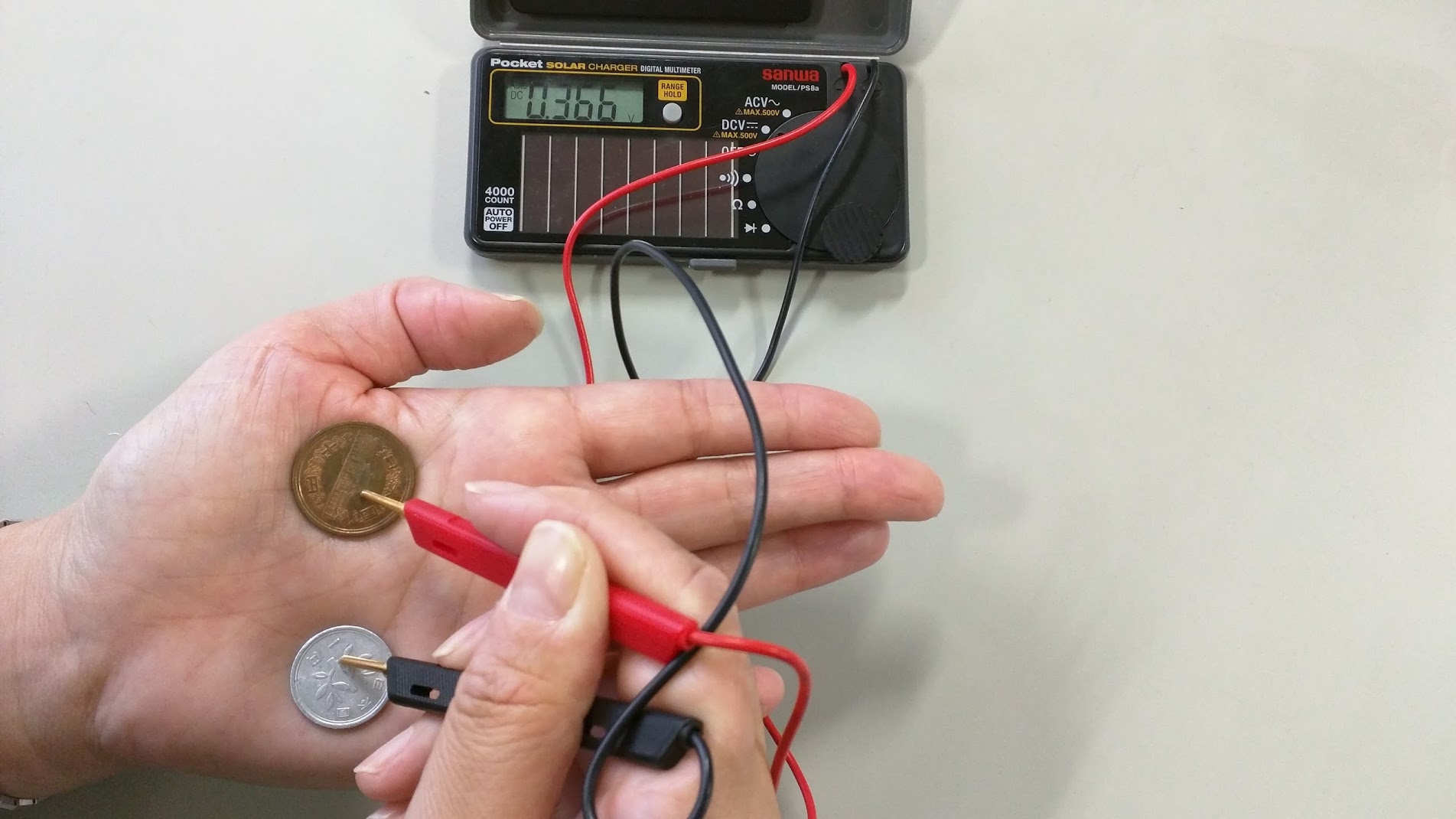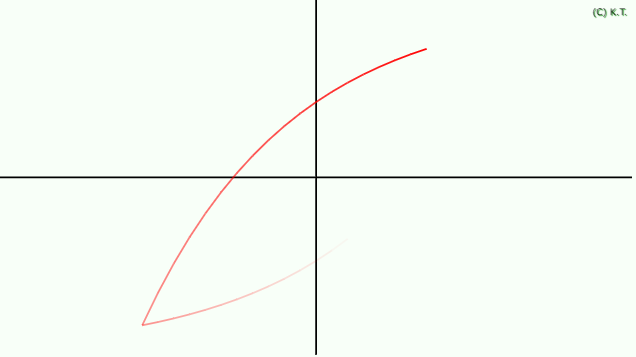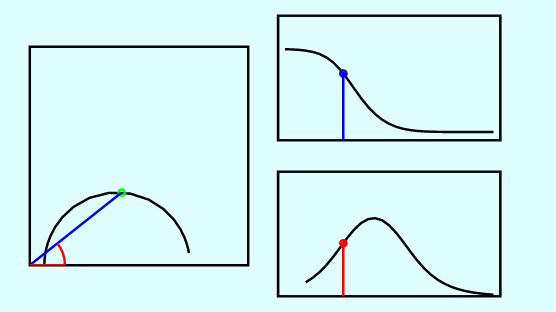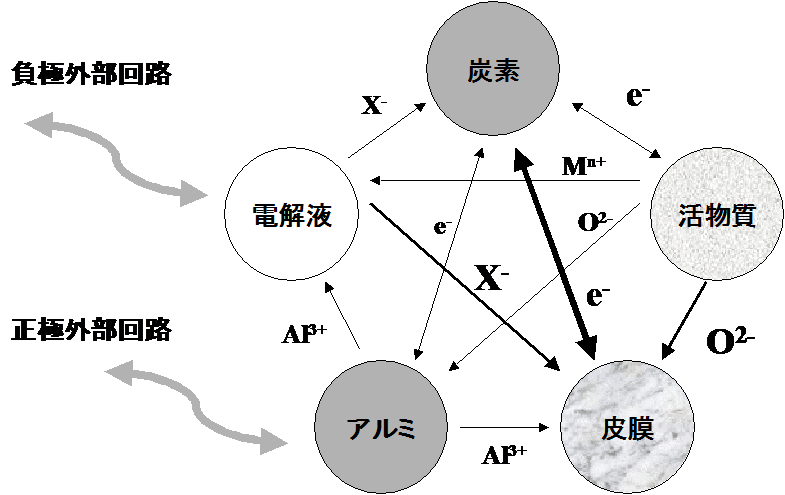2021年4月22日(木) 10:30-16:30
図
【音声テスト】正弦波(サイン波)(440Hz)
10:30~12:00 講義 第1部(90分)
12:00~12:45 お昼休み(45分)
12:45~14:15 講義 第2部(90分)
14:15~14:25 休憩(10分)
14:25~15:55 講義 第3部(90分)
15:55~16:05 休憩(10分)
16:05~16:30 講義 第4部(15分)、質疑応答、時間予備
戻る
進む
3
材料から見た電池の構造設計と工程設計
-
3-1
材料が同じでも電池性能は変わる?
-
3-2
充電式電池に求められる材料と形状の可逆性
-
3-3
スラリー塗工工程と乾燥工程による電極と導電ネットワークの形成
-
3-4
過充電時におけるバインダー樹脂と炭素粒子界面破壊
-
3-5
バインダー樹脂が種々の界面に与える影響
-
3-6
分散剤や界面活性剤の残存や異物が電池性能に与える影響
-
3-7
導電助剤と集電体との接触抵抗が電池性能に与える影響
-
3-8
電解質がマイクロショートやデンドライド形成に与える影響
-
3-9
活物質の表面やSEIが電池性能にに与える影響
-
3-10
タブリードやパッケージが電池性能にに与える影響
4
リチウムイオン二次電池のパワーマネジメント
-
4-1
単電池と組み電池、ハイブリッド蓄電システム
-
4-2
クラウドとエッジを活用した電池のモニタリング
-
4-3
リモートセンシングにおけるサイバー攻撃からの防御
-
4-4
IoTやAIを使ったバッテリシステムの制御と劣化やトラブルの診断
-
4-5
脱炭素社会に向けた再生可能エネルギー利用とV2H、超小型モビリティにおける蓄電システム
 🏠
🏠
 🏠
🏠