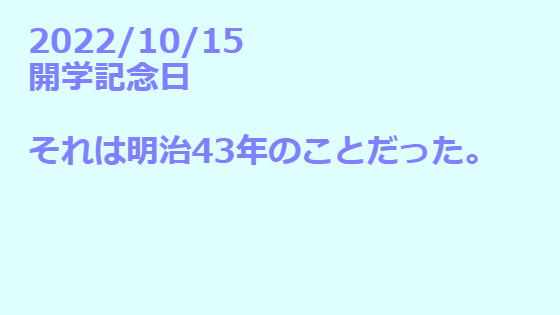2002_電気化学会秋季大会.ppt1)
リチウム二次電池は、電力平準化デバイスとして期待され、さらなる長寿命化が求められている。リチウム二次電池の正極集電体には、その高い起電力に耐え、耐食性があることと同時に活物質に充分な電流を供給されることが要求され、軽くて加工性が良く、経済的に見合う唯一の選択肢として、アルミニウムが用いられている(2)。従って、腐食によるアルミニウムの劣化や溶出、アルミニウム/電解液界面で起こりうる溶媒の酸化分解の抑制手段を見出す可能性がある正極集電体の不働態化に関する知見を得ることは重要である。
アルミニウムの不働態化に関する研究は1920年代から行われている。その陽極酸化皮膜は、ポーラス型とバリヤ型の二種類があり、バリヤ型の皮膜は高い耐電圧と誘電率を有する。1930年代にはその皮膜の電気的特性を利用して電解コンデンサに応用された。その皮膜生成機構も1940年代には高電場機構として知られるようになった(13-14)。1987?年にリチウムイオン電池の基本特許が出願されたとき、やはり、その正極集電体として高い絶縁性皮膜を生成するアルミニウムが用いられた。ところが中性水溶液中における陽極酸化皮膜に関する研究報告は数多くあるが、有機電解液中における陽極酸化皮膜に関する研究報告は数少ない。そして、それらは電解コンデンサの駆動液としての視点から、中性水溶液中で生成した陽極酸化皮膜の安定や修復に関する研究がほとんどである。また、リチウム電池の正極集電体としてのアルミニウムの研究報告は腐食に関する報告は多いが、より基礎的なアルミニウムの不働態皮膜生成に関する報告はほとんどない。
そこで、ここでは、バリヤ型皮膜を生成する代表的な中性水溶液であるアジピン酸アンモニウム水溶液中でのアルミニウムの不働態皮膜生成過程と比較しながら、代表的なリチウム電池駆動用の有機電解液であるLiBF4およびLiPF6/PC+DME溶液中におけるアルミニウムの不働態皮膜生成過程について検討した。
【関連講義】卒業研究(C1-電気化学2004~),学会発表2001@C12)
(2) 緒言(C > C1履歴 > 【200 > 学会発表@C1(2001◆H13),【2001年度(平成13)卒業研究】
仁科 辰夫,卒業研究(C1-電気化学, 講義ノート, (2001).
 🏠
🏠